こんばんは、Tomです。今日は昨日と打って変わって一日中晴れて、最高気温も10℃迄上がり、暖かい日となりました。明日は曇りが多い日ですが、それでも最高気温は13℃迄上がるようです。真冬なのにね~。
さて、今日の話題も、昨日の続きで『CROWN パワーアンプ PS-200の修理』です。今日はその4となります。昨日の記事では、メイン基板とパワーユニットの基板を再ハンダしましたが、片チャンネルの歪は解消できませんでした。いよいよメイン基板の解析となります。まずは、入力直後のOPアンプの入出力を見て、OPアンプ前なのかOPアンプ以降なのかを切り分けます。
1.PS-200をまたばらす
メイン基板の解析を行う為に、前回仮組した本体をまたばらします。何度も行っていると余り苦ではなくなってきますね。

メイン基板がお目見えしました。

2.OPアンプの前後の確認を行う
今回の課題はOPアンプの前後の信号を確認し、故障個所がOPアンプの前なのか、OPアンプ以降のドライバーなのかの切り分けを行います。これが入力直後のOPアンプです。


3.OPアンプの信号の確認
ディスプレイにPS-200の回路図を表示し、オシロスコープでOPアンプの前後の信号を当たります。
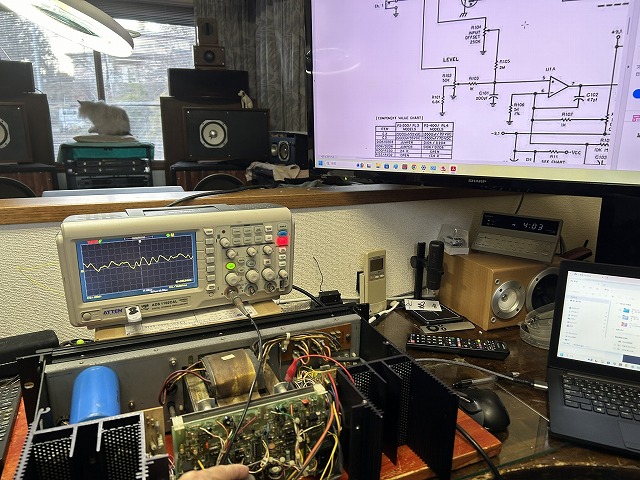
1)CH1
まず、問題のないCH1の信号を見て行きます。

① INPUT +

② INPUT ー

③OUTPUT

2)CH2

① INPUT+

② INPUT-

③ OUTPUT

酷い波形ですね。
3)CH2の入力を0にしてみる
入力アッテネータを絞って0にしてみます。

ところが出力は、こんな信号が出ています。

これは発信していますね。
4.回路図を確認する
回路図を確認すると発振防止用に47pFのコンデンサがついています。
このコンデンサが怪しいですね。

このコンデンサはC202です。
5.発振防止のコンデンサを取り出して容量を確認する
それでは、発振防止のコンデンサを取り出し容量を確認します。
1)コンデンサの取り出し


このコンデンサは、真ん中に亀裂が走っていますね~。怪しいです。

2)容量の確認
それでは、容量を確認します。
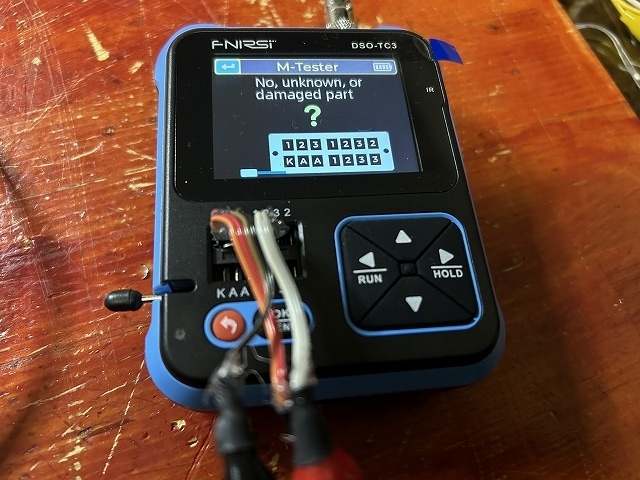
このコンデンサは壊れている様ですね。
一応、配線を替えて別の端子で再度確認します。

やっぱりNGですね。
6.正常なコンデンサを半田付けする
手持ちのコンデンサを確認した所、なんとか47pFのセラミックコンデンサを見つけました。


これを取り付けました。
7.動作確認
それでは動作を確認します。

期待したのですが、残念ながら発振は止まりませんでした。
という事は、OPアンプが怪しいですね。
OPアンプを発注してみますね。